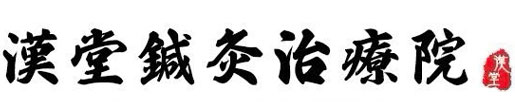治療について
当院の治療は中国伝統医学の理論や経験を基本にして、現代の研究結果を導入し、お一人ひとり様に合わせた施術、体の外側から、磨くだけではなく、本来誰もが持っている自然治癒力を高め、体質を改善し、内側から輝く健康美を手に入れる事ができるのです。鍼灸治療とは人間の気と血のバランスを整える治療方法です。体全体を巡っている経絡は気と血の通り道で、脈や舌、肌の状態を総合的に診て適したツボに鍼やお灸をして巡りを良くします。また、鍼をさすことに抵抗がある方や体力が極端に低下している場合は”てい鍼”銅でできた棒を使いますので、鍼が苦手な方も安心して受けられます。
中医学(中国伝統医学)とは
中国伝統医学(ちゅうごくでんとういがく)とは、中国において、主に漢民族によって発展させられ、2000年以上の歴史をもつ.現代で西洋医学と区別するため,中医学(ちゅういがく)と言われている.朝鮮半島や日本にも伝わってそれぞれ独自の特徴を遂げた伝統医学の総称。日本においては、東洋医学(とうよういがく)と呼ばれる。
中国から見て東洋医学という用語は日本の伝統医学を指すことがある。
中国では、中医学を専門に勉強する大学(中医薬大学6年間)があり、この大学課程の終了者が医師国家試験に合格した方は中医師と呼ばれている。診療は、漢方や鍼灸、推拿,(中国式マッサージ,按摩,整体など)基本ですが,場合によって,西洋医学の検査や治療も行う.
経絡やツボ療法
気と血がめぐる通路のことを経絡という.人体が統一体として機能できるのは経絡が全身を連絡しているからだ.経絡には経脈と絡脈がある.経脈は体の縦方向にのびる.絡脈は経脈から分かれた細い枝で,網の目のようにはりめぐらされている.
① 十二経脈
大腸経 三焦経 小腸経 肺経 心経 心包経 胃経 胆経 膀胱経 脾経 肝経 腎経
② 奇経八脈(きけいはちみゃく)
任脈 督脈 衝脈 帯脈 陰維脈いんいみゃく・陽維脈よういみゃく 陰?脈いんきょうみゃく・陽?脈ようきょうみゃく
③ ツボとは人体の反応点及び鍼などの治療点
経絡上の「ツボ」を「経穴」と呼ぶ。経絡上には約365「経穴」が存在しておる.研究で分かったのはツボを刺激することによって,血行を良くし,鎮痛,免疫を高め,自律神経のバランスをとり,内臓や器官の働きを増強するなどの色々な効能効果がある.
家庭で自分できる経絡とツボ療法
① 肩こりに効く肩井をつまむ
② 胃腸や心臓病などに効く胸腹を揉む法
③ 高血圧に効く頸部をさする法
④ 認知症防止や目疲れに効く風池
⑤ 乗り物酔い,吐き気に効く内関
⑥ イライラを治まる太衝
⑦ 養生長寿効果がある足の三里
⑧ 体弱によるめまいや婦人系に効く三陰交
⑨ 美顔に顔を擦法
⑩ 気の流れを良くする経絡を叩く法
⑪ 足腰に効く『金鶏独立』(片足立つ健康方法)
⑫ 督脈(背骨)を鍛える方法
家庭で自分できる食事療法
① 胃腸かぜ,風寒かぜ(鼻汁が多い)に効く生姜湯
鍋に水、薄くスライスした生姜一個分(約30g)と黒砂糖を適当に入れて,沸騰させて出来上がり.
② 花粉症に効く生姜漬物(お酢砂糖生姜漬物)
新鮮な生姜を適量スライスして,ガラス瓶に入れ,砂糖やお酢を適量で漬ける. 毎日朝漬物として食べる.
ショウガは中国でも古くから漢方処方に頻用されていました。生のものを生姜(ショウキョウ)、乾燥したものを乾姜(カンキョウ)と呼びます。咳を鎮め、痰を切り、嘔吐を抑えるほか、解熱や消化器系の機能亢進、腹痛、胃痛や便秘の解消,身体を温め、血行促進の作用がある
③ 心血管に効くサンザシ(山査)と黒きくらげ(黒木耳)
サンザシと黒きくらげ適量でスープを作る. 近年の研究により、サンザシには、心血管系統に強い働きがあることが発見され、さらに免疫力を高め、抗がん、抗菌、抗酸化などの作用を持つことも確認されています。
木耳(キクラゲ)とは、ビタミンD、鉄分、カルシウム、食物繊維などが豊富に含まれています。乾燥したものは、ミネラル成分が多く、血液浄化作用があるので、高血圧動脈硬化、痔、潰瘍などに効果がある.